wxWidgets とは、C++で作られたクロスプラットフォームGUIツールキットである。Windows, OS X, GTK+ などに対応している。商用版のある Q なんとかと比べて見劣りするとか言うんじゃないぞ
入手
開発中の最新版を入手しよう。wxWidgets のリポジトリは、現在 GitHub でホストされている。(ただし、Issue の管理は GitHub ではなく wxWidgets Trac を使っている。GitHub でのプルリクはできる)

wxWidgets とは、C++で作られたクロスプラットフォームGUIツールキットである。Windows, OS X, GTK+ などに対応している。商用版のある Q なんとかと比べて見劣りするとか言うんじゃないぞ
開発中の最新版を入手しよう。wxWidgets のリポジトリは、現在 GitHub でホストされている。(ただし、Issue の管理は GitHub ではなく wxWidgets Trac を使っている。GitHub でのプルリクはできる)
こういうビットマップ(1ピクセルにつき1ビット)を、整数の配列としてC言語のソースコード中に埋め込みたい:
□□□□□ ■■■■■ □■□■□ □■□■□ ■□□■■ □□□□□
2進数リテラルがあればそれを使うという手があるが、残念ながらC言語には2進数リテラルがない(ちなみに、C++にはC++14から2進数リテラルが入った。また、独自拡張で2進数リテラルが使えるコンパイラーもある)。
というわけで、自分で作ることにした。要件としては
がある。 続きを読む
C99で導入されたプリプロセッサマクロの可変長引数を使って、引数の個数によるオーバーロードっぽいことをするメモ。
参考:
可変長引数の部分への実引数が0個というのはC言語の規格的にはナシなので、引数が0個の場合には対応しない。(幾つかのコンパイラでは引数が0個でも通るが…)
GCCの場合に0個の引数を処理したい場合、GCC拡張の , ## __VA_ARGS__ みたいなやつを使うといい感じになる。
VC++で
#define CHOOSE(a0,a1,...)
#define hoge(...) CHOOSE(__VA_ARGS__)
という風に書くと、 __VA_ARGS__ の部分が一つの引数(a0)として関数型マクロに渡ってしまうので、ここに書いたコードでは CHOOSE → CHOOSE2 という風にもう一段階噛ませている。
C11の _Generic とかを使えば引数の型によるオーバーロードもできそうだ。先例:
先月はECMAScript 2015 (ECMAScript 6)が採択され、また、WebAssemblyが発表された。多分これらは現代のWebプログラミング言語の歴史に残る出来事だろう。しかし、ここ10年ぐらいのJavaScript/ECMAScriptの歴史と背景事情みたいのをまとめた文章のようなものをあまり見かけないので、ちょっとだけ書いてみることにする。(というよりは「ちょっとだけ調べてみた」の方が適切。あんまりまとまってないし)
何日までに○○しなさいというメールが届いた!けどほったらかしておいたら期限を過ぎていた!そういう経験、あるよね?
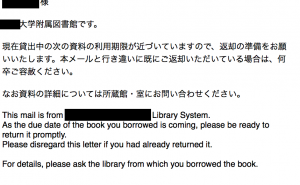 そこで、そういうメールが届いたら自動でMacの「リマインダー」に登録されるようにしよう!という話。
そこで、そういうメールが届いたら自動でMacの「リマインダー」に登録されるようにしよう!という話。
続きを読む
ECMAScriptの変数のスコープが不思議な挙動をするのはよく知られた話だ。ECMAScript 5での変数のスコープは以下のいずれかに大別される(はず)。ブロックスコープがない。
普通に使う変数が関数スコープしかないのは不便、ということで、MozillaはJavaScript 1.7(2006年頃)でlet文を導入した。が、しかし、他のブラウザには普及せず、Mozillaの独自拡張に留まることになった。
時は過ぎ、ECMAScript 5が制定され、次はECMAScript 6という流れになってきた。そして、ECMAScript 6にはlet文が導入されることになった(MozillaがJavaScript 1.7で導入したものとは微妙に仕様が違う)。めでたしめでたし。
ECMAScriptに静的型を付けたTypeScriptは、当初はlet文をサポートしていなかった。それが、TypeScript 1.4で、ECMAScript 6へコンパイルする場合のみlet文をサポートするようになった。
が、ECMAScript 6(のlet文)に対応していないブラウザはまだまだたくさんある(今調べてみたら、IE11ではES6のlet文に対応しているけど、Safariでは対応していないようだ)。できれば、TypeScriptのようなaltJS言語でlet文を使いつつ、コンパイル後のJavaScriptでは従来のvarを使ってほしい。
が、let文を従来のJavaScript (ECMAScript 5)に変換するのはそう自明なことではない。特に問題になるのは、ループ内の変数を、ループの外に持ち出される関数で使っている場合だ。[code lang=”js”]
var a = [];
for (var i = 0; i < 5; ++i) {
let x = i * i;
a.push(function() { return x; });
}
[/code]上のコードを下のように単純にvarを使うと挙動が変わってしまう。[code lang=”js”]
var a = [];
for (var i = 0; i < 5; ++i) {
var x = i * i;
a.push(function() { return x; });
}
[/code]このコードを正しくECMAScript 5に翻訳するには、即時実行関数(IIFE)を使って以下のようにしなければならない。[code lang=”js”]
var a = [];
for (var i = 0; i < 5; ++i) {
(function() {
var x = i * i;
a.push(function() { return x; });
}());
}
[/code]こういう非自明、というかパフォーマンスに影響するところがあるので、TypeScript 1.4ではES5へのコンパイル時にlet文がサポートされなかったのだろう。
が、しかし、TypeScript 1.5ではES5へコンパイルする場合でもlet文が部分的にサポートされるようになるようだ。「部分的に」というのは、ループが絡まない、変数のスコープのチェックと名前の変更で済む場合、のようだ。[code lang=”js”]
{
let x = 123;
console.log(x); // OK
}
console.log(x); // エラー
[/code]
ループが絡む、IIFEを使った変換が必要な場合は、
test2.ts(2,1): error TS4091: Loop contains block-scoped variable 'x' referenced by a function in the loop. This is only supported in ECMAScript 6 or higher.
というエラーが出た。
[code lang=”js”]
let a: Array<() => number> = []
for (var i = 0; i < 5; ++i) {
let x = i*i;
a.push(() => x);
}
a.forEach(console.log);
[/code]
GitHubでの該当するIssue/Pull Requestは以下のようだ。
let文のサポートとしては不完全とはいえ、varの関数スコープのせいで意図しない同名の変数を参照していた〜〜みたいな事故は防げると思われるので、積極的に使っていきたい。
前回はIdrisで「有界な自然数の冪乗を計算する」finPower2 : Fin n -> Fin (power 2 n) という関数を実装したが、いくつか後回しにした証明があった。今回はIdrisの証明支援機能を使ってこれを埋める。
【2017年12月18日 追記】この記事は古いTypeScript (2.0以前) を念頭に置いている。もちろん、現在のTypeScriptにも当てはまる記事はあるだろうし、TypeScript以外の言語における合併型 (union types) についてもある程度読み替えられるかもしれない。ただしElmとは “Union Types” の用法が完全に相入れないのでElmユーザーの方はお帰りください。
TypeScript 1.4について、 TypeScript 1.4.1 変更点 – Qiita という記事が目に留まった。で、その中の
直和型(Union Types)
という項目に引っかかりを感じた。:
なぜ引っかかりを感じたかというと、TypeScriptに今回導入されたUnion Typesと、巷に言う直和型というのは、異なる概念であるからだ。
注意:以下の話は型理論の専門家でもないフツーの学生が適当に書いた程度の信憑性しかありません。