人生をやっていると、大きな出費の瞬間が何回か訪れる。自動車の購入はその一つだ。
私が今住んでいる場所は都会というほどではないが大きな駅の徒歩圏内で、正直言って大人二人で生活する分には自動車はそんなに必要ない。自動車が必要ならカーシェアやレンタカーを使えば良い。だから自動車はこれまで持っていなかった。
しかし、色々あって今回自動車を購入することにした。
自動車を買うまでの流れ
自動車を買うためにはいくつか必要なものや手順がある。ざっくりと流れを書いておく。
駐車場の用意
自動車は場所を食うので駐車場が必要になる。
住んでいるマンションの駐車場に空きがあったので借りた。月3000円で、近くの月極駐車場を借りるよりも安いと思う。
3月末に不動産屋に契約に行って、5月から使用可能とした。
車を登録する際には駐車場を持っていることの証明(車庫証明)が必要で、図面を提出する必要がある。不動産屋には手数料を払って車庫証明用の図面を出してもらったが、これは現況とちょっと違っていてあまり役に立たなかった。
実印の作成
普通自動車を購入するときには実印、つまり役所に印影を登録したハンコが要るらしい。
近くのハンコ屋で作って、役所で登録する。ハンコの材質はいくつか選べたが、比較的安い木製のものにした。それでもケースと合わせて1万円近くした。
役所では印鑑証明書を発行するための専用カードをもらったが、最近はマイナンバーカードで事足りるので資源の無駄である。
これは4月末に作った。
車の選定
これが一番悩ましい。
新車か中古車か、というと、予算の都合とか納車時期とかを考慮して、中古車にした。
最初は軽自動車も考えたが、旅行や帰省で高速道路をガンガン走るとなったときに不安があるので、普通自動車にした。
他の要件は、
- 室内の空間が広いこと
- ウォークスルーができると嬉しい
- 後部ドアが電動スライドドアだと嬉しい
など。
実際に乗ってみるのも大切だ。レンタカーやカーシェアを駆使して、いくつかの車種を試した。レンタカーだと車種の指定に料金がかかる場合があるが、カーシェアは(その車種を置いている駐車場まで歩けるのなら)車種を選びやすい。
具体的な車種を挙げると、スズキのソリオにも乗ってみた。ただ、ソリオはスピードメーターが(運転席の前ではなく)中央にあるのが慣れなくて、選択肢からは外した。それとも、乗っていればいずれ慣れるのだろうか?
中古車販売店は色々あるが、初めての自動車なので安心感を優先して、メーカー系列のものにした。
あとは、Webの中古車情報を、地域と色と要件をベースに絞り込んでいった。古い車はやはり安いが、あまり古いのも不安なので、5〜6年以内に製造されたものを選んだ。走行距離は10万km以内のものを選んだ。ちなみに、私が物心ついたときに親が乗っていた乗用車は走行距離が20万kmを超えていた。
商談と購入
欲しい車が見つかったら、「商談」の予約を入れて、お店に向かう。現物を確認して、良さそうなら契約の意思を伝える。書類にサインしたり、印鑑証明書を提出したりする。一部の手続きは自分でもできるらしいが、今回はお店に委任した。
本当はここで車庫証明の書類も提出できるとスムーズだったが、持っていくのを忘れたので後日となった。
延長保証みたいなやつをつけるとナンバーを追加料金なしで選べる、ということだった。その場では希望のナンバーはないと言ったが、帰り道で良さげなナンバーを思いついたので連絡して指定してもらった。
今回選んだ車は購入が確定した後で車検をやるということなので、2〜3週間かかるということだった。ナンバーを指定すると時間がかかる、という話もあるかもしれない。
お金は一括で、銀行振込した。手数料はお店持ち(代金から手数料を差し引いた額を振り込む)だった。手数料が高いとお店に申し訳ない気がするので振り込み手段と手数料を調べたが、大きい金額の振り込みはATM・ネットバンキングだと制限があり、制限を緩和する手続きも面倒だったので窓口で振り込んだ。大きな額の銀行振込は一応「詐欺ではないことの確認」があった(動産、不動産の購入などの選択肢があった)。
決算の時期(3月とか)はセールをやって車を安く買えるという話もあるが、私が諸々の手続きや調べ物をだらだらやっていたため、間に合わなかった。それでも、他の時期であっても何かしらの安くなる理由がある場合があるようだ。
5月下旬に商談して、6月上旬が納車日となった。
自動車保険・共済
自動車に乗る上では、任意保険も事実上必須である。親(農家)に相談したらJAを勧められたのでJAの自動車共済にした。
契約には車検証の情報と自賠責の証明書の写しが必要とのことだったので、販売店に連絡してそれらが完成次第写真を送ってもらった。
販売店に車を取りに行く(→帰りは運転する必要がある)都合上、納車日から保険(共済)がスタートしてほしい。なので、納車日が確定する→保険・共済を契約する→車を受け取る、という流れになる。納車日の前日に共済の契約をした。
金額は、初めてということもあり、1年あたり10万円近くとなった。年齢が上がったり、等級が上がると安くなっていくらしい。
タイムズカーシェアを使っていると、無事故で走行した距離を提携の自動車保険に反映してくれるみたいなサービスがあるが、自分の場合は距離が足りなくて割引にならなさそうだった。
車の受け取り
自動車販売店は公共交通で行きやすい場所にあるとは限らない。商談の時はレンタカーで行ったが、自動車を受け取る場合に同じ手が使えるとは限らない。免許持ちが2人いれば行きは同乗して帰りは別の車に乗るという手はあるが、やめておいた。今回は駅から歩けない距離ではなかったので、歩いた。もっと遠かったり、日差しが強ければタクシーを使っただろう。
お店では車検証やマニュアル類を受け取って、サインをして、買った車に乗り込む。ガソリンは100km分くらい入っていた。
帰りの運転中は、まだそこまで「車を買った」という実感を持てなかった。しかし、これからあちこち運転するうちに実感が持てるようになるだろう。
ツーショット
流石に写真をそのまま貼ると背景等から家バレするので、ChatGPTにイラスト化してもらったものを貼っておく。
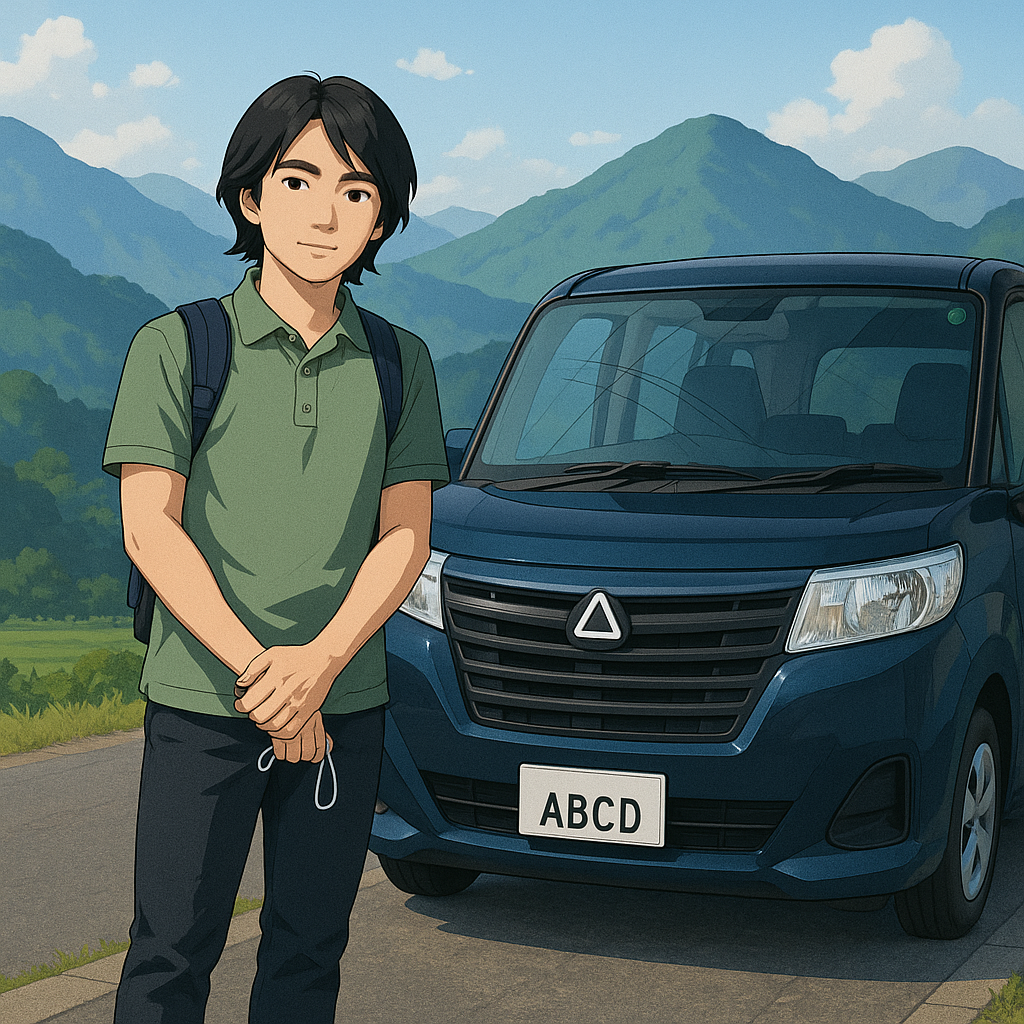
プロンプトは
- 写真をもとにイラストを作成してください。色温度は6000度にしてください。
背景はビル街に置き換えてください。車のナンバーは「ABCD」のようにダミーとわかるものにしてください。メーカーのエンブレムをダミーのものに置き換えてください。- 車のエンブレムをギリシャ文字の小文字のデルタにしてください。背景を山並みにしてください。
とした。
車は移動を自由にするか
私が生まれ育った場所は農村の車社会だった。子供が使える移動手段は、自転車か、親の運転する車だけだった。私の実家のある集落では路線バスは影が薄かった。
自転車で街まで出れば鉄道が使えたが、小遣いが多くない子供にとっては、あまり気軽に使えるものではなかった。高校になると通学で定期券を使うので定期券の範囲なら自由に動けるようにはなったが。
高卒で就職する人や、地方の大学等に進学する人は、高校卒業のタイミングで免許を取る人も多いだろう。東京の大学に進学した私が自動車の免許を取ったのは、大学1年の春休みだった。実家にMTの軽トラがあることを考慮して、友人たちがオートマの免許を取る中、必死にマニュアルの免許を取った。
ただ、大学時代は東京で暮らしていたこと、公共交通にある程度詳しくなったこともあり、免許を取っても普段から自動車を乗り回すという感じではなかった。それでも、地方に旅行に行くときや、星を見に行ったりするときは車を運転できて便利だった。
子供の頃は移動が制限されていて、今は自由に移動できる。違いは何か、と言うと、以下の2点が大きいだろう:
- 公共交通を自由に使える
- 鉄道やバスの乗り方を知っていること、交通費を持っていること
- 自動車の運転免許を持っている
- 必要に応じてレンタカーを借りられること
逆に、私の今の生活、街に住んでいて必要に応じてレンタカーやカーシェアを使える限りにおいては「自動車を所有していること」はそこまでウェイトが大きくない気がする。
仮に地方の車社会で子供を育てるとしたら、子供の移動の自由を保証するためにどうしたらいいのだろう?車社会であっても、鉄道やバスの乗り方をどこかのタイミングで教えておくべきだ。もちろん、子供の安全のことを考えると小さいうちは親のいないところで行動させたくないかもしれない。公共交通はどんどん衰退していっており、10年後には乗り方を知っていても乗れなくなっているかもしれない。それでも、親として子供のためにできることはしたいものだ。
